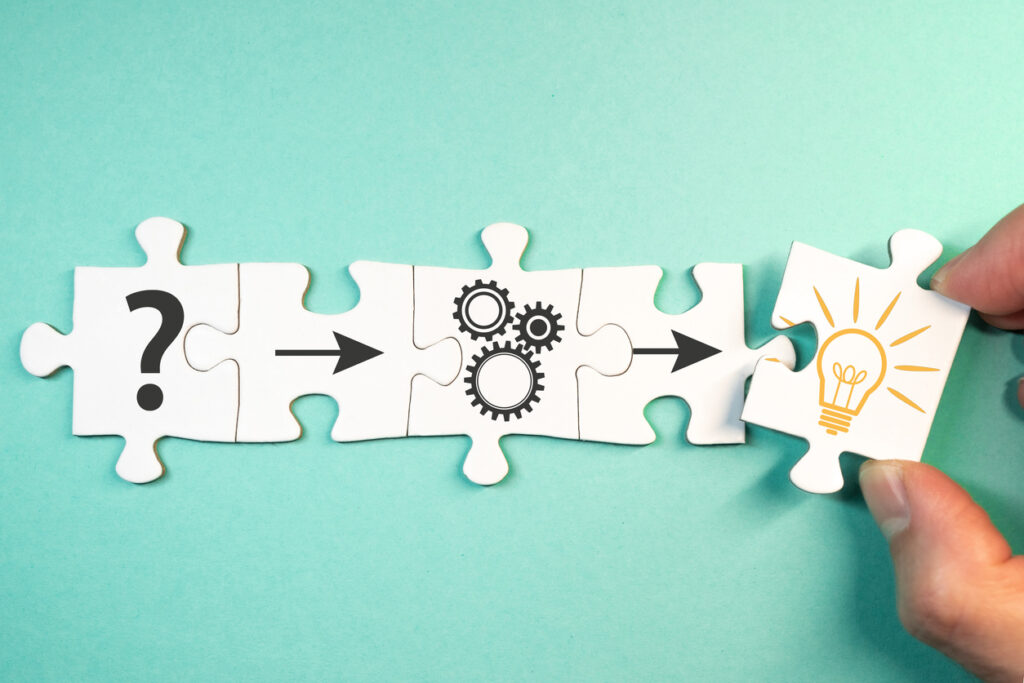ウェルビーイングとは?意味や理論・測定方法を簡単にわかりやすく解説
- 組織・人材開発
- ウェルビーイング

最近、「ウェルビーイング」という言葉を耳にすることが多くなりました。「幸福」を意味する言葉ですが、ハピネスやウェルフェアとはどう違うのでしょうか。
本記事では、まずウェルビーイングの意味を簡単にわかりやすく解説し、日本人のウェルビーイングと測定項目、ウェルビーイングに関する考え方、ウェルビーイングが注目を集めている理由についても紹介します。
受講者が没入して取り組むアクティビティ・振り返り・専門講師が行う講義をブリッジし、研修の学びを最大化
⇒受講者のスキルアップとチームビルディングをはかる「あそぶ社員研修 総合資料」を無料で受け取る
ウェルビーイングとは

WHOは、1946年の国際保健会議で採択された世界保健憲章により設立された、すべての人々の健康水準を引き上げることを目的とする機関です。世界保健憲章の前文には、「Health is a state of complete physical, mental and social well-being(健康とは、肉体的にも、精神的にも、社会的にも満たされた状態のことである)」と記されています。
参考:世界保健機関(WHO)憲章とは | 公益社団法人 日本WHO協会
また、厚生労働省は、ウェルビーイングを「個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念」としています。
つまり、ウェルビーイングとは「身体も心も健康で、生活が充実している状態」であるといえるでしょう。単に病気をしていない、弱っていないというだけでなく、人とのつながりや安定した収入、「働きがい」や「生きがい」なども、ウェルビーイングには欠かせない要素であると考えることができます。
ウェルビーイング経営については、以下の記事で詳しく紹介しています。
ウェルビーイング経営とは?取り組むメリットや施策例を紹介
ウェルビーイングと同じく「幸福」の意味を持つ言葉に、「ハピネス」と「ウェルフェア」があります。この2つの言葉とウェルビーイングの違いについて解説します。
ハピネスとウェルビーイング
ハピネス(happiness)は、「短期的・瞬間的な幸せ」の意味で用いられることが多い言葉です。たとえば、今日楽しいことがあった、ご飯がおいしい、欲しかったものが手に入ってうれしいなどです。happinessの語源はhappen(起こる、発生する)などと同じであり、偶然的な意味合いが含まれている言葉だといわれています。
対してウェルビーイングは、「多面的な幸せが持続すること」です。たとえば、毎日心穏やかに過ごせている、活力に満ちているなど、幸せな状態のなかにあることを意味します。
ウェルビーイング(well-being)は、well(良い)とbeing(~である、存在)という2つの単語が合わさってできています。今よりも「良い状態」になり、そうあり続けることがウェルビーイングなのではないでしょうか。
参考:happinessとwell-being – 富山県(PDF)
ウェルフェアとウェルビーイング
ウェルフェア(welfare)は、「福祉」の意味で用いられることが多い言葉です。立場の弱い人たちを保護する、すべての人をある一定の幸せの基準まで引き上げるというようなニュアンスが含まれています。
対してウェルビーイングは、一人ひとりにとっての「幸せ」「より良い状態」を追求するものであるといえるでしょう。
また、ウェルフェアは、ビジネスシーンでは「福利厚生」の意味で使われることもあります。そのため、従業員のウェルビーイングを実現することが「目的」であり、その「手段」がウェルフェア(福利厚生)であるという考え方もあります。
日本人のウェルビーイングと測定項目
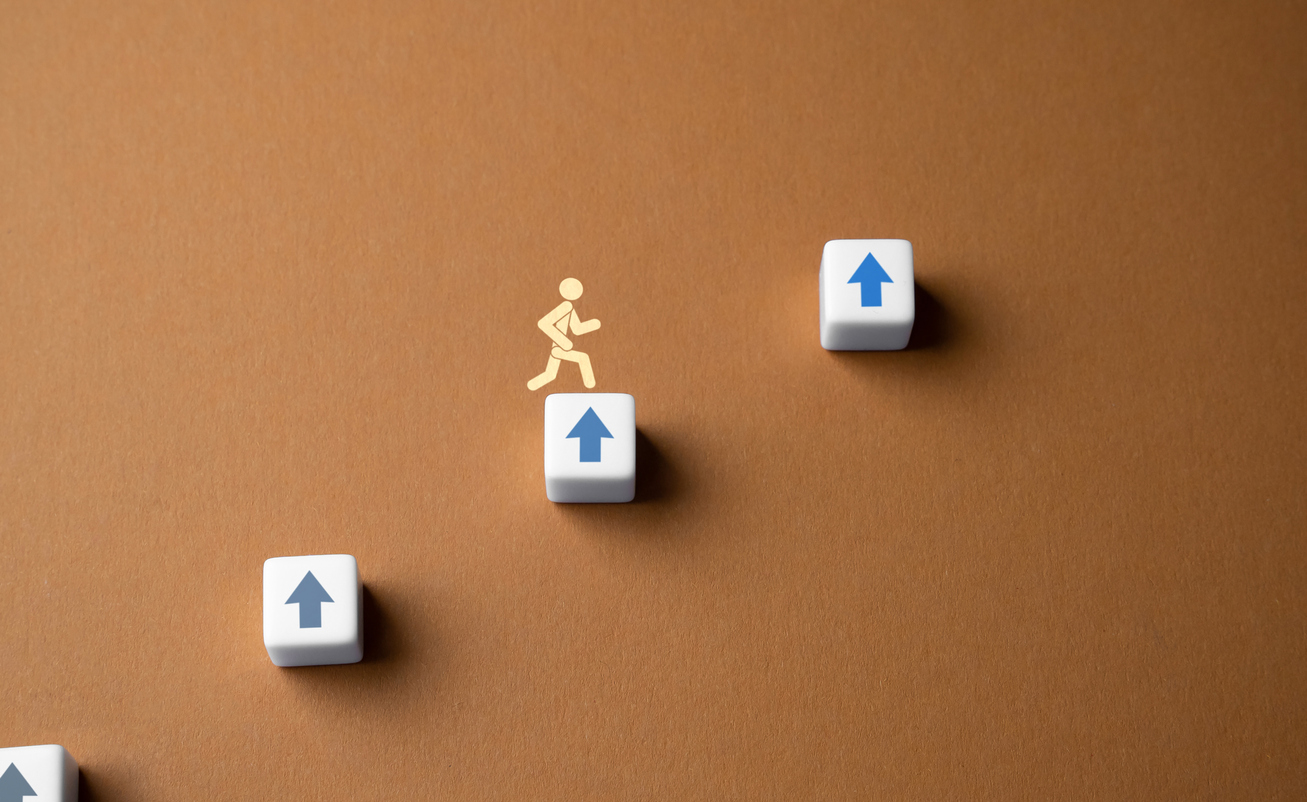
OECDの「Better Life Index」
OECDが公表している「Better Life Index」(以下、BLI)では、「物質的な生活条件」と「生活の質」に不可欠な11の項目から、国全体の幸せを測定しています。
【物質的な生活条件】
- 住宅
- 収入
- 雇用
【生活の質】
- 共同体
- 教育
- 環境
- ガバナンス
- 医療
- 生活満足度
- 安全
- ワーク・ライフ・バランス
日本のBLIは?
BLIのホームページでは、国ごとのデータが公表されており、幸福度を比較することができます。2023年3月時点で公表されているデータを見てみると、日本はほかの国に比べて、多くの分野で満たされている国であることがわかります。たとえば、
- 有給の仕事に就いている人の割合(15歳~77歳)
- 教育システムの質(国際学生評価プログラム「PISA」における読解力、数学、科学のスコア)
- 出生時平均寿命
- 「水質に満足している」と答えた人の割合
などが、いずれもOECD平均を上回っています。
しかし、
- 一人あたりの平均世帯純調整可処分所得(※可処分所得=いわゆる「手取り収入」のこと)
- 選挙の投票率
- 生活に対する一般的な満足度
などは、OECD平均を下回る結果となっています。生活に対する一般的な満足度は、0から10のスケールで評価します。OECD平均が6.7点であるのに対し、日本人は平均6.1点でした。11の項目別に見ると、日本は「収入」「ガバナンス」「ワーク・ライフ・バランス」のスコアが特に低くなっています。
参考:Japan – OECD Better Life Index
ウェルビーイングに関するモデル・定義

ウェルビーイングは、基にした学問や研究内容によっても考え方が異なるため、さまざまな測定方法や指標があります。ここからは、「幸せとは何か」を考えるときに取り上げられることが多いモデル・定義を紹介します。
1.セリグマン博士の「PERMAモデル」
「PERMA(パーマ)モデル」は、ポジティブ心理学の父と呼ばれるアメリカの心理学者、マーティン・E・P・セリグマン博士が提唱した考え方です。幸せを構成する以下の5つの要素の頭文字を取って名付けられました。
- Positive emotion(ポジティブ感情)
うれしい、おもしろい、楽しい、希望、感謝、安らぎ など - Engagement(没頭)
仕事やスポーツ、趣味などに時間を忘れるほど夢中になる、積極的にかかわること - Relationship(人間関係)
良好な人間関係を築けている、人とのかかわりを楽しめている - Meaning(意味)
自分が存在している意味や目的を感じられる - Accomplishment(達成)
何かを達成する感覚、または達成に向けて進んでいくこと
ポジティブ心理学は、セリグマン博士により1998年に創設された、フラーリッシュ(持続的な幸福)を追求する学問です。ポジティブ心理学では、上記5つの要素を意識することでウェルビーイングが高まり、幸せに近づくと考えられています。
このPERMAモデルに基づき、これらの要素を測定できる「PERMA-Profiler」という心理検査も開発されています。
2.タル・ベン・シャハー博士の「SPIREモデル」
「SPIRE(スパイア)モデル」は、前項で紹介したポジティブ心理学研究の中心人物の一人である、心理学者のタル・ベン・シャハー博士が提唱した、ウェルビーイングの指標です。こちらも、以下の5つの頭文字を取って名付けられました。
- Spiritual Well-Being(精神のウェルビーイング)
意義のある人生を送れている、今を楽しめていること - Physical Well-Being(身体のウェルビーイング)
身体に気を使い、心身のつながりを活かすこと - Intellectual Well-Being(知性のウェルビーイング)
自分から深い学びに取り組み、経験を広げていくこと - Relational Well-Being(人間関係のウェルビーイング)
自分自身と他人にとって良い関係を築けていること - Emotional Well-Being(感情のウェルビーイング)
心穏やかに過ごせる、自ら辛い感情から脱することができること
タル・ベン・シャハー博士は、このなかでも「人間関係のウェルビーイング」が最も重要であるとしています。ですが、どれか1つを高めるだけでは、ウェルビーイングは実現しません。5つの指標をバランスよく高めていくことで、ウェルビーイングにつながるとしています。
3.ギャラップ社の定義
国ごとの幸福度を測る調査の1つに、国連が毎年行っている「World Happiness Report(世界幸福度報告)」があります。この調査には、アメリカの調査会社のギャラップ(Gallup)社が実施しているグローバル調査「Gallup World Poll」の調査結果が利用されています。そのギャラップ社が定義するウェルビーイングの構成要素は、以下の5つです。
- Career well-being(キャリアのウェルビーイング)
仕事、家事、育児、勉強など、自分の時間の大半を占めていることを楽しめている、情熱を持って取り組めている - Social well-being(人間関係のウェルビーイング)
周囲の人と強い信頼と愛情でつながり、良好な関係を築けている - Financial well-being(経済的なウェルビーイング)
安定した収入があり、資産をうまく管理・活用できている - Physical well-being(身体的なウェルビーイング)
心身ともに健康で、日々の活動を実行するエネルギーが十分にある - Community well-being(地域社会とのウェルビーイング)
地域社会とのつながりを感じられる
ギャラップ社は、これらの要素は信仰や文化などにかかわらず、すべての人に共通するものだと考えています。また、前項で紹介したSPIREモデル同様、どれか1つが満たされていてもウェルビーイングは実現せず、5つの要素それぞれをより良くしようと行動することが重要だとしています。
参考:ウェルビーイング研究~ギャラップ社の定義 – 富山県(PDF)
4.Googleが提唱した「デジタルウェルビーイング」
デジタルウェルビーイングとは、2018年にGoogleが提唱した概念です。決まった定義はありませんが、デジタルデバイスとのかかわり方を見直して、心と身体の健康を保つことを意味します。
インターネットやパソコン、スマートフォンなどが普及し、私たちの暮らしはとても便利なものになりました。しかし、これらに依存しすぎると、健康や日常生活に悪い影響が生じることがあります。
たとえば、デジタルデバイスを長時間利用すると、目や首・肩など身体に負担がかかるだけでなく、睡眠障害や、記憶力・判断力の低下などにつながる恐れもあります。また、チャットやSNSで簡単にコミュニケーションが取れるようになったことで、「周囲の動きを常に把握しておかないと話題についていけなくなる」というプレッシャーやストレスが生まれ、孤独感や不安感に襲われたり、うつ状態になってしまったりすることもあります。
デジタルウェルビーイングの実現に貢献するために、Googleが提供するAndroidのスマートフォンには、「Digital Wellbeing」というアプリが搭載されており、スマートフォンの利用時間をチェックしたり、アプリやウェブサイトを閲覧する時間に上限を設けたりすることができます。
また、近年、デジタルデバイスとしばらく距離を置き、ストレスを軽減する「デジタルデトックス」という取り組みも注目されています。
ウェルビーイングが注目されている3つの理由

近年、ウェルビーイングが注目されるようになったのはなぜなのでしょうか。考えられる原因は、大きく3つあります。
1.GDPに代わる指標の必要性の高まり
GDPとは、「Gross Domestic Product」の略称で、日本語では「国内総生産」といわれています。経済的な豊かさを測る指標で、国内で生まれたモノやサービスの付加価値を合計したものです。内閣府が公表している資料を見ると、2010年以降、日本は名目GDP3位をキープしており、経済的には比較的豊かな国であるといえます。
しかし、先ほど紹介したように、BLIにおいては生活に対する一般的な満足度がOECD平均を下回っており、ギャラップ社の調査結果が利用されている国連の「World Happiness Report2022」においては、日本の幸福度は世界54位と、決して高いとはいえない順位となっています。経済的な豊かさも幸せを構成する1つの要素ではあるものの、それだけでは幸せを測れないということがわかります。また、価値観や生き方の多様化、新型コロナウイルスの影響などにより、「幸せとは何か」について考える人も多くなっているのではないでしょうか。
こうしたなかで、GDPに代わる新たな指標の必要性が高まっており、ウェルビーイングが注目を集めているのです。日本では、日本経済新聞社が中心となり、2021年3月に「Well-being Initiative」が発足しました。ウェルビーイングという概念と、GDPに代わる新たな指標GDW(Gross Domestic Well-being:国内総充実)を、2030年以降の社会アジェンダにすることを目的とし、さまざまな活動を実施しています。
参考:ABOUT | GDW
2.生産年齢人口の減少
少子高齢化が進む日本では、生産年齢人口(15~64歳)が減少しており、2050年には、2021年から29.2%減の5,275万人まで減少すると見込まれています。
この影響で、すでに多くの業界で人手不足が深刻な課題となっています。加えて中小企業は、離職率も高い傾向があります。離職の理由としては、待遇面だけでなく「会社の将来が不安だった」や「職場の人間関係が好ましくなかった」というものも多く見られ、採用難の時代に優秀な人材を確保するために、従業員のウェルビーイングの実現に取り組む企業も増えているのです。
厚生労働省も、このようななかで日本経済を維持・発展させていくためには、「就業面からのウェルビーイングの向上と生産性向上の好循環」をつくっていく必要があるとしています。
参考:ー令和3年雇用動向調査結果の概要ー – 厚生労働省(PDF)
3.SDGsに対する関心の高まり
SDGsは、「Sustainable Development Goals」の略称で、日本語では「持続可能な開発目標」と呼ばれています。2015年9月に開催された国連サミットにおいて、加盟国の全会一致で採択された国際目標です。持続可能でより良い世界を実現するために、2030年までに達成するべき17の目標と169のターゲットで構成されています。
目標3には「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する(Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)」とあり、すべての人のウェルビーイングを実現することが掲げられています。
参考:JAPAN SDGs Action Platform | 外務省
また、ウェルビーイングは「身体も心も健康で、生活が充実している状態が持続すること」を意味しますので、実現に向けた取り組みは、目標3以外にもさまざまな目標につながると考えられます。たとえば、従業員がいきいきと働けるよう職場環境を整備したなら、目標8「働きがいも 経済成長も」に、出産・育児後の女性社員が復帰しやすいよう、新たな働き方を導入したなら、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」にも貢献できるでしょう。
ウェルビーイングはSDGsにも深くかかわる概念であるため、達成に向けた取り組みが世界中で広がる今、より注目されるようになったのではないでしょうか。
ウェルビーイングの企業事例については、以下の記事で詳しく紹介しています。
ウェルビーイングの企業事例9選!実現に向けた取り組みを紹介
【講義+アクティビティ一体型】あそぶ社員研修

「あそぶ社員研修」は、受講者全員が没入して取り組むアクティビティ・振り返り・講義をブリッジすることで学びを最大化させ、翌日から業務で活かせる知識・スキルが身につく講義・アクティビティ一体型の研修プログラムです。
研修の特徴
- チームビルディング効果が高いアクティビティを通して受講者のエンゲージメントを向上させられる
- 誰もが没入できる「あそび」を取り入れた体験型アクティビティで受講者の主体性を引き出す
- 複数回のフィードバックによって学びを定着させる
まとめ

ウェルビーイングに決まった概念はありませんが、「身体も心も健康で、生活が充実している状態が持続すること」という意味合いで用いられています。
経済的な豊かさも幸せを構成する1つの要素ではありますが、イコールではないという認識が世界中に広がっています。そのため、GDPに代わる新たな指標の必要性が高まっており、国内外でウェルビーイングに関する研究が進められています。
本記事で紹介したように、ウェルビーイングにはさまざまな考え方や測定方法、指標があります。どのような状態を「幸福」と感じるかは、人それぞれです。この機会に、自分にとっての「幸福」とは何か、考えてみてはいかがでしょうか。
「あそぶ社員研修」は、受講者全員が没入して取り組むアクティビティ・振り返り・講義をブリッジすることで学びを最大化させ、翌日から業務で活かせる知識・スキルが身につく講義・アクティビティ一体型の研修プログラムです。
アクティビティが受講者の主体性を高めてコミュニケーションを促進させ、スキルアップやチームビルディングをはかれます。
この記事の著者
雪国生まれ、関西在住のライター・ラジオパーソナリティ・イベントMC。不動産・建設会社の事務職を長年務めたのち、フリーに転身。ラジオパーソナリティーとしては情報番組や洋楽番組を担当。猫と音楽(特にSOUL/FUNK)をこよなく愛し、人生の生きがいとしている。好きな食べ物はトウモロコシ。